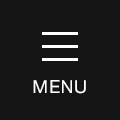
 企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
スライドレクチャー 第1回(2月27日)
2026年2月3日(火)午後1時より受付開始
| 日時 | 2026年2月27日(金) 午前11時30分~12時15分 (開始15分前より、会場の講堂前にて受付を行います) |
|---|---|
| 場所 | 根津美術館 講堂 |
| 定員 | 100名 |
| 講師 | 担当学芸員 |
| 参加費 | 参加は無料ですが、入館料が必要です。 ※確実にご入館いただくため、事前の日時指定予約をお願いします。 |
| 参加方法 | 2026年2月3日(火)午後1時よりオンラインで受付開始します。 2月3日(火)午後1時より、この画面に設置される「参加申込み」ボタンをクリックして表示される「イベント申込みフォーム」に必要事項を記入のうえ、送信してください。※ご本人様以外のお申し込みも可ですが、参加者1名につき1回のお申し込みが必要です。 入力いただいたアドレスに、受付完了メールが届きます。当日は、受付完了メールのプリントアウトか、このメールを表示できるスマートフォン等をお持ちになり、受付にてご提示ください。 申込みは、先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。 |
 「青山茶会」:2026年3月7日(土)開催の茶会について
「青山茶会」:2026年3月7日(土)開催の茶会について
応募受付は終了しました。
| 内容 | 根津美術館では茶道に習熟した方を対象として、より一層、お茶や美術に対する造詣を深め、当館に親しみを持っていただくために会員制の『青山茶会』を運営しており、その一環として2025年度は年3回の茶会を開催しております。このたび3回目の茶会を開催するにあたり、会員以外の方でもご参加いただけるように、若干数ではありますが、茶席券をご用意いたしました。数に限りがございますので、参加ご希望の方は、下記の申込方法をご覧の上、根津美術館受付にてお早目にお申込みくださいますよう、ご案内申し上げます。 |
|---|---|
| 茶会概要 | 2026年3月7日(土)10時00分~15時30分 *受付時間 9時40分~14時30分 席入りの時間は当日受付順の時間指定制となっています。 ・茶席 庭園内茶室「弘仁亭」 御席主: 今日庵 ・展観席 庭園内茶室「披錦斎」 根津美術館所蔵の茶道具取合せを展示。 学芸員が解説し、茶碗を手にとってご鑑賞いただけます。 ・点心席 本館地下1階講堂 |
| 定員 | 若干 |
| 参加費 | 1名様 28,000円 (茶席、展観席、点心席、入館料、税込) ※現金でのお支払いのみとさせていただきます。 |
| 参加申込方法 | 事前申込制。1月31日(土)10時00分より申込開始。開館時間内に当館受付にて承ります。 |
| 注意事項 | ・1回にお申し込みいただける枚数は、おひとり1枚までです。 ・電話、FAX、メールではお申込みできません。 ・キャンセル待ちはできません。 ・災害、停電などのやむを得ない事情による開催中止を除き、お支払いいただいた参加費の 返金はできません。 ・雨天の場合も開催いたします。 ・茶会当日は、茶会にふさわしい服装にてご参加ください。 ・お子様連れでの参加はご遠慮ください。 ・茶会に参加される方は、茶会当日、駐車場はご利用いただけません。 |
 企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
特別催事 素浄瑠璃「壺坂観音霊験記 -沢市内より山の段-」
応募受付は終了しました。
| 内容 |
根津美術館が所蔵する武器・武具はほぼ、明治時代の実業家・光村利藻の蒐集品で成り立っています。大阪生まれの神戸育ちの光村は、二代目越路太夫から浄瑠璃を習う、大の文楽ファンでもありました。そこで企画展「英姿颯爽 根津美術館の武器・武具」に合わせ、素浄瑠璃を楽しむ会を企画いたしました。現在の人形浄瑠璃文楽座を牽引する演者である、豊竹呂勢太夫さんと鶴澤燕三さんをお迎えし、迫力ある演奏をお楽しみいただきます。演奏の前には、呂勢太夫さんに浄瑠璃の聴きどころ、ご自身の床本や見台の蒐集についてもお話をうかがいます。 詳細は添付チラシをご覧ください。 |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年3月8日(日)午後1時~2時(12時45分開場) |
| 場所 | 根津美術館 講堂 |
| 定員 | 100名(自由席) |
| 参加費 |
2,000円(税込) ※入館には別途催事当日の入館料が必要です。当館ホームページから事前の入館予約をお勧めいたします。または催事当日に当日入館券を当館受付でお求めください。 |
| 参加申込方法 | 2月3日(火)午後1時より、当館ホームページにて参加券を販売いたします。(クレジットカード決済のみ、キャンセル不可) |
| 注意事項 | ・中学生以上対象。小学生以下のお子様連れの参加はご遠慮ください。 ・開演中の入退場はできません。 ・当館受付、電話、FAX、メールではお申込みできません。 ・災害、停電などのやむを得ない事情による開催中止を除き、お支払いいただいた参加費の 返金はできません。 |
 企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
講演会「光村コレクションの刀剣」
2026年2月3日(火)午後1時より受付開始
| 日時 | 2026年3月14日(土) 午後2時00分~3時30分 (開始30分前より、会場の講堂前にて受付を行います) |
|---|---|
| 場所 | 根津美術館 講堂 |
| 定員 | 100名 |
| 講師 | 久保恭子氏(元日本美術刀剣保存博物館事業課長・専門学芸員) |
| 参加費 | 参加は無料ですが、入館料が必要です。 ※確実にご入館いただくため、事前の日時指定予約をお願いします。 |
| 参加方法 | 2026年2月3日(火)午後1時よりオンラインで受付開始します。 2月3日(火)午後1時より、この画面に設置される「参加申込み」ボタンをクリックして表示される「イベント申込みフォーム」に必要事項を記入のうえ、送信してください。※ご本人様以外のお申し込みも可ですが、参加者1名につき1回のお申し込みが必要です。 入力いただいたアドレスに、受付完了メールが届きます。当日は、受付完了メールのプリントアウトか、このメールを表示できるスマートフォン等をお持ちになり、受付にてご提示ください。 申込みは、先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。 |
 特別催事〔茶会〕はじめての茶席 ―2026年 春―
特別催事〔茶会〕はじめての茶席 ―2026年 春―
| 内容 | 根津美術館では、企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」(2/14 〜3/29)期間中の3月15日(日)、茶道未経験の方を対象とした茶会「はじめての茶席-2026年 春-」を庭園内の茶室「披錦斎」で開催いたします。 この時期ならではのお道具の取り合わせ、季節の和菓子、そして薄茶一服を実際のお茶室でお楽しみいただきます。初めてお茶会に参加される方を対象に、お茶室の見どころやお菓子、お茶の召し上がり方など、当館職員がわかりやすくご説明いたします。 参加ご希望の方は、下記「申込方法」をご覧の上、美術館の受付にてお申込みください。定員になり次第受付終了となりますので、お早めにお申込みくださいますようご案内申し上げます。 |
|---|---|
| 日時 | 2026年3月15日(日) (第1回)10:15 – 11:00 *定員に達しました (第2回)11:10 – 11:55 *定員に達しました (第3回)12:30 – 13:15 *定員に達しました (第4回)13:25 – 14:10 *定員に達しました (第5回)14:20 – 15:05 *定員に達しました (第6回)15:15 – 16:00 *定員に達しました ※開始時間の15分前に地下1階の「茶室口」に参加券をご持参の上、お集まりください。 |
| 場所 | 根津美術館 庭園内茶室「披錦斎」 |
| 定員 | 各回13名 |
| 参加費 | 1名様 2,500円 *薄茶と季節の和菓子、懐紙、楊枝を含みます。 ※入館には別途催事当日の入館料が必要です。当館ホームページから事前の入館予約をお勧めいたします。または催事当日に当日入館券を当館受付でお求めください。 |
| 参加申込方法 | 事前申込制。1月22日(木)より開館時間内に当館受付にて承ります。 ※2/2(月)~2/13(金)は展示替えのため休館。 ※受付は定員になり次第終了いたします。 |
| 注意事項 | ・お電話、FAX、メールではお申込みできません。 ・キャンセル待ちおよびお時間の変更はできません。 ・1回にお申込みいただける人数は、おひとり3名様までです。 ・災害、停電などのやむを得ない事情による開催中止を除き、お支払いいただいた参加費の返金はできません。 ・雨天の場合も開催いたします。 ・中学生以下のお子様連れでの参加はご遠慮ください。 ・当日欠席される場合は、集合時間までにご連絡ください。 ・ミニスカート、素足での参加はご遠慮ください。 ・洋装の方は白ソックスをご持参いただき、茶室に入る際、ご着用ください。 ・アクセサリー類は外してご参加ください。 ・茶室内での写真撮影はお控えください。 ・茶会に参加される方は、茶会当日の駐車場はご利用いただけません。 |
 特別催事 茶室で楽しむ椿の花芸
特別催事 茶室で楽しむ椿の花芸
| 内容 | さまざまな器物に椿をあしらった「百椿図」にちなみ 当館茶室にて、その絵の情景を現代風にアレンジしていただきます。 |
 |
|---|---|---|
| 日時 | 2026年3月19日(木)~ 3月21日(土) 午前10時から午後4時まで ※ただし、21日(土)は午後3時まで |
|
| 場所 | 庭園内茶室 弘仁亭・無事庵 | |
| 展示制作 | 花芸安達流・二代主催 安達曈子氏 | |
| 参加方法 | 事前申込は不要です。 ※ご観覧は無料ですが、入館料を別途お支払ください。 |
 企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
企画展「英姿颯爽 -根津美術館の武器・武具-」
スライドレクチャー 第2回(3月20日)
2026年2月3日(火)午後1時より受付開始
| 日時 | 2026年3月20日(金) 午前11時30分~12時15分 (開始15分前より、会場の講堂前にて受付を行います) |
|---|---|
| 場所 | 根津美術館 講堂 |
| 定員 | 100名 |
| 講師 | 担当学芸員 |
| 参加費 | 参加は無料ですが、入館料が必要です。 ※確実にご入館いただくため、事前の日時指定予約をお願いします。 |
| 参加方法 | 2026年2月3日(火)午後1時よりオンラインで受付開始します。 2月3日(火)午後1時より、この画面に設置される「参加申込み」ボタンをクリックして表示される「イベント申込みフォーム」に必要事項を記入のうえ、送信してください。※ご本人様以外のお申し込みも可ですが、参加者1名につき1回のお申し込みが必要です。 入力いただいたアドレスに、受付完了メールが届きます。当日は、受付完了メールのプリントアウトか、このメールを表示できるスマートフォン等をお持ちになり、受付にてご提示ください。 申込みは、先着順で定員になり次第、締め切らせていただきます。 |
