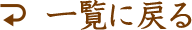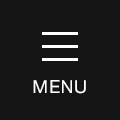- 日本・平安時代 12世紀
- 1合
- 高12.3cm 奥行34.4cm 幅38.2cm
- [50111]
平文は、平脱(へいだつ)ともいい、漆塗りの地に金属の薄い板金を嵌め込んで文様をあらわす象嵌技法のひとつである。中国で唐時代に盛んに行なわれた技法で、正倉院にも作例が伝わっている。日本製である平文の遺例はきわめて少なく、本作はそのひとつである。長方形合口造(あいくちづく)りの箱で、総体を黒漆塗りとし、蓋表に大きく宝相華文を配した唐風のシンメトリーな文様は、銀の薄板であらわされ、細部を毛彫りで仕上げている。現在は銀が黒く酸化しているが、往時は黒漆地と白く光る銀のコントラストが鮮やかだったことであろう。