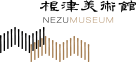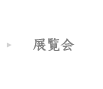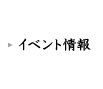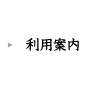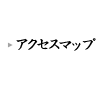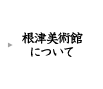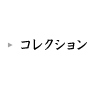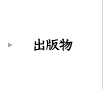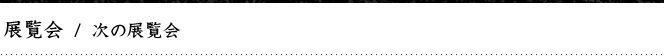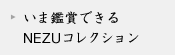企画展
企画展
英姿颯爽
根津美術館の武器・武具- 2026年2月14日(土)~3月29日(日)

| 休館日 | 毎週月曜日 ただし2月23日(月・祝)は開館、翌火曜休館。 |
|---|---|
| 開館時間 | 午前10時~午後5時(入館は閉館30分前まで) |
| 入場料 |
オンライン日時指定予約 一般1300円 学生1000円 *障害者手帳提示者および同伴者は200円引き、中学生以下は無料 |
| 会場 | 根津美術館 展示室1・2 |
根津美術館のコレクションの中で、武器・武具はちょっと特殊な存在です。実は初代根津嘉一郎は「刀はわからない」と公言しており、好んで蒐集していないからです。しかし明治42年(1909)に、実業家・光村利藻(みつむら としも・1877–1955)の3,000点におよぶ武器・武具コレクションを一括購入。優れた作品群の海外流出を危惧した英断は大規模な散逸を防ぎ、その体系的な蒐集の特性を守ることになりました。当時からは半減したものの、当館の武器・武具は現在も、ほぼ光村コレクションで形成され、未だ往事の内容をよく伝えています。
本展覧会では、これら質の高い、洗練された武器・武具コレクションから選りすぐりをお楽しみいただきます。

-
鮫研出刻鞘大小拵
(刀装具)後藤一乗・池田隆雄作 - 1揃 木胎漆塗/赤銅地ほか
- 日本・江戸~明治時代 19~20世紀
根津美術館蔵 - 月山貞一(がっさん さだかず)に発注した刀身のために光村利藻があつらえた拵。多く蒐集した後藤一乗(ごとう いちじょう)の作品から揃金具を選び、不足を池田隆雄(いけだ たかお)に補作させたのであろう。廃刀令により消滅の危機に瀕した刀剣文化を護った、光村コレクションを象徴する作品のひとつ。

-
御伽噺図揃金具
小川知恒作 - 1揃 素銅地ほか
- 日本・江戸時代 19世紀
根津美術館蔵 - 「桃太郎」「猿蟹合戦」「舌切り雀」といったおとぎ話を題材としたカワイイ刀装具。作者の小川知恒は大坂の装剣金工で、現存する作品は非常に少ない。コレクションにはこのような希少作例が多く含まれており、資料的価値も高い。


- 太刀 銘 来國俊
- 1口 鍛鉄製
- 日本・鎌倉時代 13世紀
根津美術館蔵 - 来國俊は鎌倉時代後期の山城国来派を代表する刀工。細身の優美な姿にゆるやかに反りがつき、華美に流れすぎないつくりに品格を感じさせる。

-
牡丹蝶図鐔
加納夏雄作 - 1枚 鉄地
- 日本・江戸~明治時代 19世紀
根津美術館蔵 - 加納夏雄は帝室技芸員にも任じられた幕末明治の金工の雄。本作は、牡丹の柔らかく幾重にも重なる花弁を、立体的にその質感まで表現した優品である。